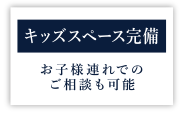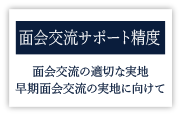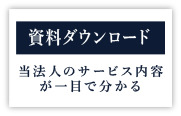- HOME
- お知らせ
お知らせ
2025/11/21
離婚と住宅ローン付きの家 ― 売却と持ち続けるケースの違い
離婚のご相談でよくあるのが,住宅ローンが残っている家をどうするかという問題です。
夫婦で共有名義になっていたり,片方の名義でもう一方が保証人になっている場合など,整理が必要なポイントが多くあります。
今回は,よくある2つのケース――「売却する場合」と「家を持ち続ける場合」について解説します。
1.家を「売却する」ケース
(1)売却してローンを完済できる場合
家の売却価格が住宅ローン残高を上回る場合,売却代金でローン
を完済できます。
完済後に残ったお金(いわゆる「売却益」)があれば,それを夫
婦で分け合うことになります。たとえば共有名義なら,持分割合
に応じて分配します。
(2)売却してもローンが残る(オーバーローン)場合
家を売ってもローンが残る場合,金融機関の同意を得て任意売却
を行う方法があります。この場合でも,残った債務(残債)は名
義人が引き続き支払う必要があります。離婚によってもローン契
約は自動的には変更されないため,どちらがどのように支払うの
かを明確にしておくことが重要です。
2.家を「持ち続ける」ケース
(1)家の名義人(夫または妻)が住み続ける場合
たとえば夫名義の家で,夫が住宅ローンを支払い続け,夫が同じ
家に住み続けるという形です。双方が合意をすればとてもシンプ
ルです。
ただし,「住宅ローンが夫婦共有名義になっている」「片方が連
帯保証人になっている」場合は,離婚してもその責任は残ります
ので注意が必要です。
連帯保証人を外すには金融機関の承諾が必要でし,金融機関はロ
ーン名義の変更には消極的ですので金融機関への相談が不可欠で
す。
(2)子どもの養育などを理由に妻が住み続ける場合
家の名義が夫でも,子どもの養育のために妻と子が住み続けるケ
ースもあります。
この場合,夫がローンを支払い続けるなら,家の使用をどう位置
づけるかを明確にしておく必要があります(例えば,「使用貸借
」や「財産分与としての使用権設定」など)。片方に持ち分を贈
与する場合は,贈与税のリスクが発生する場合もあります。
更に,ローンの支払いが滞ると競売にかけられるリスクもあるた
め,慎重な取り決めが必要です。
家は生活の基盤であり,同時に大きな財産でもあります。
安易に「どちらが住むか」「誰が払うか」を決めてしまうと,後々の支払いトラブルや登記問題につながることもあります。
金融機関との交渉や財産分与の手続きは専門的ですので,早い段階で弁護士へご相談をお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。

お知らせ
2025/11/20
裁判ってなに?実際の手続きや流れについて
裁判と聞くと、法廷で「異議あり!」と立ち上がり話し出すシーンや、証人として呼ばれた方が新事実を話し始めて回りがどよめく…などテレビドラマのシーンを思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、実際の裁判はもっと地道で、準備書面や書証など様々な書類のやり取りなど、手続きの積み重ねで進んでいきます。
様々な事例の裁判があると思いますが、今回は民事裁判を例にお話していきます。
まず、裁判は訴状を作成し、裁判所に提出するところから始まります。
訴状の提出先は、請求額が140万円以下の場合、被告の住居地を管轄する簡易裁判所となり、140万円以上の場合は地方裁判所になります。
裁判所が訴状を受理後、裁判期日の日程調整を行い、被告に訴状の副本が送達されるという流れになります。
訴状の副本等を受け取った被告は、裁判所が指定する期日までに“答弁書”を提出する必要があります。
その後双方裁判所に出廷し、自分の主張を記載した書面や証拠を提出するなどして、争点を明確にします。
ただ、この期日も通常は約1ヶ月に1回程度しか行われないため、事案の複雑さや、和解が成立などしないと1年以上長引くケースもあります。
裁判所は平日しか開いておらず、普段の連絡や期日はすべて平日のため、裁判が長期間続くとなると日常生活に影響が出てくるかもしれません。
専門家に任せることで、書面作成や裁判所への出廷などが最低限になるため、無駄な時間や費用を避けることが出来ます。
・離婚を検討しているが、養育費や財産分与で折り合いがつかない…
・交通事故の過失割合で揉めている…
・事業を経営しているが資金繰りがうまくいかず、法人破産を検討している…
・親族が亡くなり、遺産整理で揉めている…
など、様々なお悩みがあるかとおもいます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回無料相談を実施しており、経験豊富な弁護士がしっかりとお話をお伺いするため、ご予約制となっております。
まずは、ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
1人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
New Entry
Archive
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月