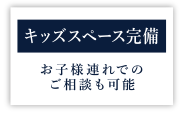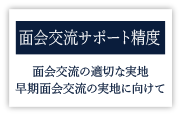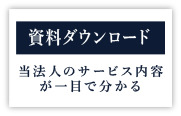- HOME
- 弁護士ブログ
弁護士ブログ
2022/09/01
親権者変更の手続きについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士の坪井智之です。
最近、当事務所長崎オフィスでは、親権者変更の手続きに関するご相談を多数お受けしております。
離婚の際に事情があって親権を取れなかった方も子どもの面倒を見ることができる体制になって改めて親権を取りたい
という方は多数います。
親権者変更の手続きは簡単に認められる手続きではありませんが、監護状況や子の意思等をしっかり吟味していくことで
子の親権者を変更することが子の福祉に資する場合には、親権者変更は認められます。
親権者の変更は当事者の合意では変更できず、必ず裁判所へ申立てしないといけません。
親権者の変更手続きなど複雑な手続きは一度弁護士へご相談下さい。親権者変更の手続きやその流れ、対応方法について
ご説明いたします。
親権者変更、面会交流、離婚、財産分与でお悩みの方は
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にお問合せ下さい。
離婚事件、刑事事件、債務整理、相続、交通事故でお悩みの方は、
一度当事務所へご連絡下さい。
初回相談料無料、土日祝日対応可能な当事務所長崎オフィス代表弁護士の坪井が
あなたの悩みに寄り添います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/08/26
強要罪で不起訴処分になりました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士の坪井智之です。
強要罪に関する刑事事件について、被害者としっかりと示談が成立し、
不起訴処分で事件が無事に終了しました。
強要罪は、罰金刑はないため、認め事件の場合、
示談が成立しない場合、公判請求される可能性が高いです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、
日々様々な刑事事件のご相談をお受けしており、解決しております。
・不起訴にしたい
・逮捕、勾留されたくない
と言う方は、早期に弁護士事務所へご相談ください。
早期示談交渉を行い、不起訴処分や逮捕勾留されないように対応致します!!
刑事事件で悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへ
お気軽にお問合せ下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/08/24
面会交流について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚に関するご相談を日々多数お受けしております。
離婚で問題となるのは、親権や面会交流が多く、子どもに関する問題であるためしっかりと協議を行う必要があります。
面会交流は、子どもが非監護親と接する重要な機会であり、「よく連れ去り等」を理由として拒絶するケースがありますが、ルールを守った上での面会交流は子どもにとって極めて重要なものであるため、その機会を確保する必要があります。
なお、虐待があるなど離婚時に面会させることが危険な場合は除きます。
しかし、重要なのは、面会交流のルールです。
しっかりと面会交流のルールを定め、非監護親も安心して面会交流ができる環境を作ることが子どもにとっても、非監護親にとっても安心した良い面会交流の機会になります。
「面会交流」がしたいという方、一度当事務所へお電話ください。
面会交流の調停の経験豊富な弁護士が貴方の面会交流の手助けを行います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/08/23
養育費増額・減額調停
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、養育費の増額調停・減額調停等のご依頼も多数お受けしております。
一度取り決めた養育費は適正ですか?
10年前に取り決めをした際、著しく低い金額で合意した方はいませんか?
離婚の際の養育費を定めた時期と比較して、年収が大幅に変動した方はいませんか?
一度養育費の金額を定めても経済状況や家庭状況に変動があった場合には、養育費の増額調停や減額調停を行うことができます。
離婚後の事情の変動によって養育費は変更することができます。
養育費の金額が適正か、養育費の支払い関係にお悩みの場合には、当事務所長崎オフィスにお気軽にお問合せ下さい。
適正な養育費の支払いを行い、子どもにとってもっともよい環境整備を図りましょう。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/08/21
初回相談料無料について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
では、初回相談用無料で様々な法律相談を日々お受けしております。
長崎県内において初回相談料無料の事務所は、まだまだ多くはありません。
離婚事件、刑事事件、相続事件、交通事故事件、債務整理事件などは、まずは初回相談料無料の事務所でご相談されることをお勧めします。
ご相談したとしても一切依頼をする必要はありません。
ご相談だけでも大丈夫です。
電話相談やZOOM相談による電話相談も無料です!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚事件、刑事事件、債務整理、交通事故、相続などの解決実績豊富な弁護士が様々な相談を無料でお聞きしますので、ご安心してご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
New Entry
Archive
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月