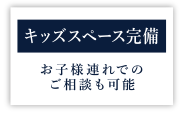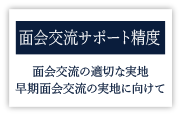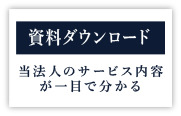- HOME
- 法律相談コラム
法律相談コラム
2022/02/24
犯罪被害者支援制度 Q&A 2
Q 犯罪の被害によって生じた財産上の損害や、精神的苦痛を受けているので、犯人(加害者)に損害賠償を請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
A 犯罪の被害により生じた損害については、民事上の問題として、加害者と被害者が交渉する(示談交渉)か、民事訴訟を起こして損害賠償を請求する必要があります。
示談交渉の場合は、加害者の方から弁護士を通じて、被害者に対し、示談交渉してくる場合があります。
このような場合、相手が弁護士であることから、被害者の方は示談に応じないといけないと感じ、相手方の言うままの示談を行ってしまうことがあります。
納得のいかない状況で示談を行うと、後に、「本当に反省しているのだろうか」、「相手から報復してこないだろうか」と不安を感じことがあります。
このような時は、被害者の方の代理人として、弁護士を立て、加害者側と適切な示談交渉をすることをお勧めします。
また、当長崎オフィスの弁護士坪井は、カウンセリングの資格を有しており、犯罪被害に遭われたご相談者様の心のケアも心がけております。
経験豊富な弁護士が、被害に遭われた方のための最善の方法をアドバイスいたします。
弁護士ブログ
2022/02/24
離婚事件の取り組みについて
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,内縁についてご説明します。
内縁とは,男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み,社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず,婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。
内縁関係は,内縁関係が不当破棄された場合に,損害賠償請求が請求できるのかとの相談を受けることが多くあります。
内縁については,法律婚の場合とほぼ同様の効果を認める場合がありますが,法律婚は区別される場合もあり,内縁関係をいずれの場合と捉えるのかについての判断には困難を要する場合もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
内縁関係に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福長崎オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士 松本 匡志
お知らせ
2022/02/24
長崎オフィス離婚専門サイトを立ち上げました
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の離婚事件、離婚に関する様々な事件(子の引き渡しや監護者指定)などを解決した弁護士が在籍しております。
その解決してきた実績を踏まえ、当長崎オフィスの弁護士が離婚事件、離婚に関する様々な事件についてどのような理念のもと、解決してきたのかを皆様にわかりやすく説明すべく、離婚専門サイトを立ち上げました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、事務所立ち上げ当初より、離婚事件に力を入れており、香川県では離婚相談件数上位ベスト3に入ると言っても過言ではないほどの件数の相談をお聞きしてきた実績を有しております。
長崎県においても、長崎市の方以外にも、長崎県の大村や佐世保等、幅広い地域の方からのご相談をお受けしております。
当事務所では、「離婚に強い」「離婚事件と言えば」「離婚事件に真摯に取り組んでいる」と言っていただけるよう、離婚事件を専門分野の一つとして取り扱っております。
離婚でお悩みの方は、一度当事務所長崎オフィスの下記離婚専門ページをご覧いただき、初回相談料無料の当事務所長崎オフィスへご連絡ください。
離婚問題に悩んだら弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/02/24
アンケート結果
ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:ホームページ、弁護士ドットコム、ココナラ法律相談
ご意見・ご感想:相談することで少し気が楽になりました。ありがとうございました。
お客様の声
2022/02/21
アンケート結果
ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士会
ご意見・ご感想:弁護士さんの柔らかい雰囲気が安心して相談させて頂く事ができました。次の段取りへの説明等も分かりやすかったです。