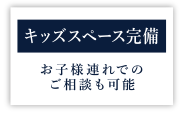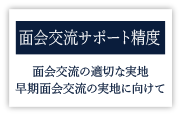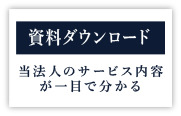- HOME
- 法律相談コラム
お知らせ
2022/05/30
長崎オフィス 弁護士募集のお知らせ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、以下のような弁護士を募集しております。
・長崎県で弁護士として働きたい方
・香川県で弁護士として働きたい方
・将来的に支店長として支店を担いたい方
・民事事件、刑事事件を問わず様々な事件を経験したい方
・交通事故、刑事事件、離婚事件、債務整理等の事件を多数経験したい方
等を積極的に募集しております。
長崎オフィスは今年1月できたばかりのため、一緒に事務所を発展させてくれる弁護士を募集しております。
私たちと一緒に働きませんか?
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所長崎オフィスでは、皆様からの応募をお待ちしております。
詳しくは、担当弁護士の坪井智之までお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/05/26
アンケート結果
ご相談目的:男女トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:ネットから
ご意見・ご感想:分かりやすい説明でよかった。初めての事だったけど親身になってくれた。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士ブログ
2022/05/23
給与所得者等再生
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続を数多く取り扱っています。
今回は,給与所得者等再生についてご説明します。
給与所得者等再生は,給与など定期的収入で,変動幅が小さく,将来の収入が一定以上ある債務者が利用できる手続きです。
弁済すべき額は,給与所得者等再生の場合,可処分所得の2年分・最低弁済基準額・清算価値を比較して,一番高い金額を返済しなければなりません。
そのため,可処分所得額の2年分が最も高い金額となる事が多く,給与所得者等再生は,小規模個人再生よりも返済額が高くなりがちです。
可処分所得は,次の式で求めます。
可処分所得 = 収入 -(社会保険料+所得税・住民税などの公租公課)- 最低生活費
つまり,「可処分」とは,毎月の給与のうち,税金や生活費を差し引いた,給与所得者が自由に使用できる所得のことです。
メリットとしては,小規模個人再生と異なり,再生計画に対して債権者からの反対等を受けても,再生計画に対する認可を得ることができる点があります。
そこで,債権者の反対が多く小規模個人再生が利用できない場合には,給与所得者等再生を申し立てることになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,個人再生手続のご相談はもちろん,それ以外にも債務整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
まずは,お気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/05/23
アンケート結果
ご相談目的:刑事事件
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコムから
ご意見・ご感想:休日に対応していただき、不安が解消されよかった。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
お知らせ
2022/05/20
入所のご挨拶
この度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスに
入社させていただくことになりました中川理絵と申します。
私は、前職では社会福祉士として様々なお悩みを抱えた方のお話を聞かせていただいておりました。そうした中で法律に関わるお悩みを抱えた方が多くいらっしゃいました。
しかし、弁護士に相談することは敷居が高く、大変緊張するという方も多く、一歩踏み出すことは大変な勇気がいることだと感じました。
そうした方々のご不安を少しでも和らげ、安心して弁護士に相談をしていただけるようご相談者様と弁護士との橋渡しができる存在になりたいと思い入社いたしました。
ご相談者様のお気持ちに寄り添い、安心して相談ができると思っていただける環境を作っていきたいと考えております。ご相談者様お一人おひとりのお話を丁寧にお聞きし、確実に弁護士におつなぎしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
事務局 中川理絵