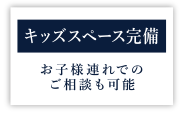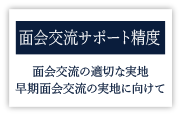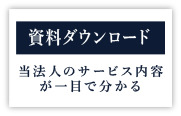- HOME
- 法律相談コラム
弁護士ブログ
2025/11/18
相続放棄と財産放棄の違いとは? (借金を引き継がないための正しい選択)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、たくさんの相続放棄の手続きを取り扱っています。
今回は、長崎で相続について悩んでいる方に向けて、「相続放棄」と「財産放棄(遺産放棄)」の違いについて、わかりやすくご紹介します。
相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所に申し出ることで「相続人としての立場を手放す」手続きです。
この手続きをすると、財産も借金も一切引き継がなくて済みます。
ただし、「相続が始まったことを知ってから原則3か月以内」に手続きしないと、放棄できなくなることもあるので注意が必要です。
相続が発生したら、なるべく早めに専門家に相談するのがおすすめです。
財産放棄(遺産放棄)って?
財産放棄は、他の相続人に「遺産は受け取らない」と伝えるだけのものであり、家庭裁判所での手続きは不要です。
ただし、相続人であることには変わりないので、借金がある場合はその一部を負担する可能性もあります。
借金を引き継ぎたくない場合は、正式な「相続放棄」の手続きを選ぶ必要があります。
他にもある相続の方法
相続には、こんな選択肢もあります。
• 単純承認
財産も借金もすべてそのまま引き継ぐ方法。特に手続きをしなければ、基本的にこの形になります。
• 限定承認
相続で得た財産の範囲内で借金を返済し、残った分だけを受け取る方法です。
財産の内容がよくわからないときに選ばれることが多く、家庭裁判所への申し出が必要です。
• 相続放棄
財産も借金もすべて放棄し、相続人としての立場もなくなる方法で、借金が多い場合などに有効です。
なお、相続放棄の手続きが終わると、あとから撤回することはできません。
そのため、事前にしっかりと財産の状況を調べて、家族とも話し合ったうえで判断することが大切です。
相続の判断は、法律のことだけでなく気持ちの面でも負担が大きく、ケースによっては複雑になることもあります。
長崎で相続放棄や遺産分割、後見人制度などについて相談したい方は、相続に詳しい弁護士に話を聞いてみるのがおすすめです。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、相続放棄はもちろん、債務整理や遺産分割など幅広い相続の問題に対応しています。
初回相談は無料ですので、「ちょっと聞いてみたいな」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
お客様の声
2025/11/18
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:わからない
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:初めて聞く意見だったり法律などを教えて頂きこれからの活動にとても勉強になりました。ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2025/11/17
アンケート結果
ご相談目的:相続トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:短時間で的確なご指導をいただき、ありがとうございました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お客様の声
2025/11/13
アンケート結果
ご相談目的:学校トラブル
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:うまく話せない中でも、丁寧に聞いてくださりありがとうございました。
アドバイスをいただいた内容をもとに、対応していってみようと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
弁護士ブログ
2025/11/12
長崎で刑事事件多数扱う弁護士在籍!逮捕されたらすぐにすべき行動と弁護士の役割
突然の逮捕や警察の呼び出し——。
ご家族やご本人が刑事事件に関わったとき、「どうすればよいのか」「誰に相談すべきか」と不安になる方は少なくありません。
今回は、長崎で刑事事件を多数扱う弁護士が在籍している弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所が、逮捕後の流れや早期に弁護士へ相談すべき理由をわかりやすく説明します。
★刑事事件の基本的な流れ
刑事事件では、逮捕から起訴、裁判までの流れを正しく把握・理解することが非常に重要です。
①逮捕・勾留
勾留決定日を1日目として10日間勾留、勾留延長されたらさらに10日間、最長20日間勾留されます。
この期間中に、弁護士が早期に接見(面会)し、本人の状況を確認します。
※在宅事件の場合も、定期的に打ち合わせし、進捗を把握して法的アドバイスを行います。
②起訴・不起訴の判断
弁護士が迅速に動くことで、不起訴処分の可能性を高めることができます。
③裁判手続き
起訴された場合でも、弁護士が証拠や証言を精査し、依頼者にとって最善の弁護活動を行います。
★逮捕直後に弁護士へ相談すべき理由と刑事弁護における弁護士の役割
刑事事件では初動の速さがその後の結果を大きく左右します。弁護士は依頼者の権利を守る最後の砦として、次のような重要な役割を果たします。具体的には次のようなサポートを行います。
①接見(面会)によるアドバイス
通常の一般接見では、面会時間(約15分)や回数(1日1回)に制限がありますが、弁護士の場合、365日24時間対応可能で、回数制限なく面会することができます。また、弁護士は立会人なしで接見できるため、取調べで不利な供述を避けるための助言や、今後の見通しを説明でき、時間を有効活用して法的助言をすることが可能です。
早期の保釈請求が可能になりますし、取調べで不利な供述を避けることができます。
お勤めの場合は、職場への対応・保釈請求などもサポートします。
また、接見禁止が付いている場合でも、弁護士がご本人とご家族との架け橋となり、サポートすることができます。家族への連絡もスムーズにとることができるのでご本人もご家族も非常に安心です。
②勾留に対する異議申立て
弁護士は、勾留の理由や必要性を争う「準抗告」や「勾留取消請求」を行い、迅速に釈放を目指します。
③被害者との示談交渉
示談は不起訴処分や量刑軽減に大きく影響します。
弁護士が間に入り、警察や検察と連携しながら被害者との交渉をスムーズに進めます。
④裁判での弁護活動(無罪主張・量刑軽減)
起訴前は、警察による厳しい取調べを受けることが多く、弁護士は正確な法的知識に基づいて、取調べへの対応方法や今後の見通しについて助言します。
起訴後は、保釈が認められない限り、身体拘束を受けたまま裁判に臨むことになります。弁護士は保釈請求を行うとともに、裁判を進めるために必要な証拠資料を閲覧・精査し、公判での弁護活動を行います。
このように、弁護士へ早期に相談することで、起訴を回避し、不起訴処分を得られる可能性が高まります。
刑事事件は初動がすべてです。
逮捕・刑事事件でお困りなら、すぐに弁護士へ相談することが大切です。刑事事件は、一刻を争う事態です。もう少し様子を見ようと思っている間にも、状況は悪化してしまうことがあります。長崎で刑事弁護に強い弁護士に早めに相談し、最善の対応を取りましょう。
逮捕前や逮捕直後のご相談は、土日祝対応可能な弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所へご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、刑事事件はもちろん、交通事故や不貞慰謝料請求、養育費や親権などの離婚相談も承っております。
すこしでもお悩み事がある方は、まずはご気軽にお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスは初回相談30分無料です。