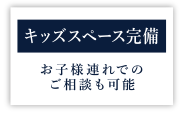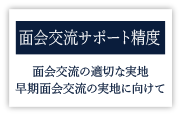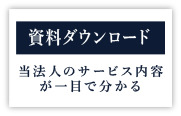- HOME
- 弁護士ブログ
弁護士ブログ
2026/01/27
子の引き渡しでお悩みの方
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、日々様々な案件の相談をお受けしております。今回は子どもの引渡しについてお話させていただきます。
1. 子どもを連れて出て行かれた
ある日突然、パートナーが子どもを連れて家を出て行ってしまった。このような状況に直面したとき、「どうしたらいいのか」「どこに相談すればいいのか」と深い不安と孤独を感じていらっしゃることと思います。
当事務所長崎オフィスでは、「子の引き渡し」や「子どもの連れ去り」に関するご相談を数多くお受けしております。特に、配偶者が子どもを連れて突然別居したケースは非常に緊急性が高く、一刻も早く対応することが必要となります。
2. 子の引き渡し請求とは
子の引き渡し請求とは、「現在子どもと一緒に生活をしている人から、自分のもとへ返すよう裁判所に求める手続」のことです。
・配偶者が無断で子供を連れて出て行った
・面会交流のあと、子供を返してもらえない
・一時的な預かりと言っていたのに子供が戻ってこない
このような場合に、法的手段を用いて子供を取り戻すための手続きです。
3.何よりも早さが重要な理由
子の引き渡し請求において最も重要なのは“早さ”です。子の引渡し請求は、子供の生活の安定性を最も重視するため、時間が経てば経つほど、現状の生活が安定していると判断される傾向にあります。
時間がたつほど元の生活へ戻ることが難しくなってしまうため、早急に対応することが必要です。
もし、現在子どもを連れて突然別居された、子どもに会えていない、帰してほしいのに話し合いが進まない、どこに相談したらいいか分からないと言った状況でお困りであれば、 早急に弁護士等へ相談をすることをお勧めします。
子供の問題は、待っていても自然に解決することは難しく、むしろ、従前お伝えしたように、時間が経つほど解決が難しくなってしまうのが現実です。
当事務所は長崎オフィスでは、子の引き渡し請求について豊富な対応実績を有しており、あなたとお子さんにとって最善の環境を取り戻すため、法律の専門家として全力でサポートさせていただきます。子どもの連れ去りや監護についてお悩みの方は、まずは、弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでお気軽にご連絡ください。初回相談は無料、対面でのご相談、電話でのご相談等ご相談者様の希望に応じて対応させていただきます。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士ブログ
2026/01/13
自己破産しても免除されない債務とは?非免責債権の具体例と注意点
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、自己破産・個人再生・任意整理など、幅広い債務整理手続を取り扱っております。
長崎で借金問題に悩まれている方からも、「自己破産すればすべての借金がなくなるのか?」というご相談を多くいただきます。
今回はその中でも「自己破産」に焦点を当て、自己破産をしても免除されない債務(非免責債権)について詳しくご説明いたします。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、免責許可が出れば原則として借金が全額免除される制度です。
ただし、すべての債務が免除されるわけではなく、法律上「免責されない債務」が定められています。
免除されない主な債務(非免責債権)
以下のような債務は、自己破産をしても原則として免除されません。
• 税金(住民税・所得税など)
• 詐欺・横領など悪意の不法行為による損害賠償
• 故意・重大な過失による人身損害賠償(例:交通事故)
• 養育費の未払い分
• 未払い給与
• 故意に申告しなかった債務
• 罰金や科料
• 生活保護費の返還請求
とくに交通事故の損害賠償などは、事故の内容や過失の程度によって免責の可否が分かれるため、慎重な判断が必要です。
なぜ免除されないのか?
これらの債務は、社会的責任や倫理的義務が強く求められるものです。
たとえば、税金や罰金は公共の秩序を維持するためのものであり、養育費や損害賠償は他者の生活や権利を守るためのものです。
自己破産によってこれらまで免除されてしまうと、社会的な不公平が生じるため、法律で除外されています。
自己破産を検討する際の注意点
非免責債権に該当するかどうかは、裁判所の判断による部分もあります。
特に交通事故や損害賠償などは、事案の内容によって結果が変わることがあります。
そのため、自己破産を検討する際は、【長崎 弁護士 債務整理】に精通した専門家に相談することが重要です。
状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、手続きがスムーズに進み、再スタートへの道が開けます。
まずはご相談ください(初回相談無料)
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、自己破産手続に精通した弁護士が多数在籍しております。
長崎オフィスでも対応可能ですので、金銭的にお困りの方や債務整理をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
弁護士ブログ
2025/12/23
⚖️ 遺産相続のお悩み解決!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、皆様の日常生活で直面する様々なお悩みに日々真摯に向き合っております。特に遺産相続や離婚、債務整理等、人生の大きな転機に関わるご相談を多くお受けしています。
そこで今回は遺産相続についてお話させていただきます。
1.遺産分割って何?
あまり聞き慣れない方も多くおられるかもしれませんが、簡単に言えば、故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった際に、残された財産を相続人のみんなで話し合って分ける手続きのことです。
故人の財産(預貯金や不動産など)は、亡くなった瞬間は一時的に相続人全員の共有財産となります。この共有状態を解消し、「誰が何をどれくらい受け取るのか」を具体的に決めていくという手続が遺産分割と言います。
- 遺産分割の進め方について
遺産分割には、大きく分けて3つの進め方があります。
①遺産分割協議
相続人全員で直接話し合い、分割方法を決めること
②遺産分割調停
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、話し合いによる解決を目指す手続きのこと
③遺産分割審判
遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合に、裁判官が公立に基いて分割方法を決定する手続きのこと。調停がまとまらなかった場合に自動的に移行する
遺産に関しての話し合いは、当人同士で解決することもありますが、感情的になってしまい話し合い自体うまく行かないことも多くあります。弁護士を代理人とすることで、冷静に交渉を行うことができ、感情的な対立を避けることができるため、スムーズな解決を目指すことができます。
また、調停や審判となった場合は、書類の提出や、裁判所への出廷等は弁護士が行わせていただきます。
当事務所長崎オフィスのでは、遺産相続だけでなく、離婚に伴う財産分与や親権の問題、生活再建のための債務整理(自己破産、任意整理など)といった様々な分野のご相談をお受付しております。今回お話しさせていただいた、相続問題については、単に財産を分けるだけでなく、その後のご家族の未来にも関わる大切なことです。
「遺産分割の相談がしたいけど、どこから手を付けていいか分からない」「他の相続人と直接話したくない」など、少しでもお悩みがあれば、ぜひ一度、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご相談ください。初回のご相談は無料となっており、経験豊富な弁護士がご相談者様にとって最善の解決策をご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士ブログ
2025/12/02
【長崎 弁護士 少年事件】逮捕から審判までの手続きと弁護士の役割
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、刑事事件の弁護に力を入れており、毎月多数の私選弁護事件のご相談・ご依頼をいただいております。
とくに【長崎 弁護士 少年事件】に関するご相談は、保護者の方の不安が大きく、早期の対応が重要です。
今回は、少年事件で逮捕された場合に、どのような手続きが進むのかを段階ごとにご説明いたします。
ご家族が突然の逮捕に直面した際、冷静に対応するための参考になれば幸いです。
1.【逮捕】未成年が警察に拘束される
14歳以上の少年が事件を起こした場合、警察に逮捕されることがあります。
逮捕後は最大48時間以内に検察へ送致され、警察署で取り調べを受けます。
この段階では、家族でもすぐに面会できないことが多く、弁護士による接見が重要です。
弁護士は黙秘権の説明や供述への助言を行い、勾留を避けるための意見書提出など、早期から重要な支援が可能です。
2.【勾留または家庭裁判所送致】
検察官は、勾留請求(最大20日間)または家庭裁判所への送致を選択します。
家庭裁判所に送致された場合、少年は少年鑑別所に収容され、観護措置が取られます(原則4週間、最大8週間)。
弁護士が早期に関与することで、勾留や観護措置の回避、示談交渉の開始など、少年の拘束期間を短縮する働きかけが可能です。
3.【家庭裁判所での調査と審判】
鑑別所では心理検査や面談が行われ、家庭裁判所調査官が事件の経緯や家庭環境を調査します。
この結果は「調査票」として裁判官に提出され、審判での判断材料となります。
少年審判は非公開で行われ、裁判官が少年や保護者の話を聞き、処分を決定します。
主な処分には以下があります:
• 保護観察(家庭で更生)
• 少年院送致(施設での教育)
• 児童自立支援施設への送致
• 審判不開始(教育的配慮による処分なし)
弁護士は、少年の更生意欲や家庭の支援体制を調査官や裁判官に伝え、誤解を防ぐ役割も担います。
4.【逆送・触法少年】
重大事件や非行歴がある場合、家庭裁判所から検察官に「逆送」され、成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります。
一方、14歳未満の少年は「触法少年」とされ、刑事責任は問われず、児童相談所による保護措置が取られます。
5.まとめ
少年事件は、家庭裁判所や少年鑑別所を含む独特の手続きがあり、保護者にとっても精神的負担が大きいものです。
弁護士が早期に関与することで、
• 不利な供述を防ぐ
• 勾留・観護措置の回避に働きかける
• 示談交渉を円滑に進める
• 審判に向けた準備を整える
といった支援が可能になります。
万が一、お子さまが逮捕された場合は、慌てず冷静に対応し、少年事件に精通した【長崎 弁護士 刑事事件】の専門家へ早めにご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスでは、少年事件をはじめ、交通事故、相続、債務整理など幅広い分野に対応しております。
初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
弁護士ブログ
2025/11/26
貸したお金が返ってこない!!~すぐできる対処法とトラブルを未然防ぐポイント~
日常生活の中で、友人や知人、職場の同僚などから「お金を貸してほしい」と頼まれることがあります。身近な相手だからこそ、深く考えずにお金を貸してしまうことも少なくありません。しかし、金銭の貸し借りには常にトラブルのリスクが隠れています。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでも「貸したお金がかえって来ない」「相手と連絡が取れなくなった」といった金銭の貸し借りに関するトラブルのご相談を多くお受けしています。
今回は金銭トラブルを未然に防ぐための基本のポイントやトラブルが発生した際の対処法を分かりやすく解説します。
①口約束だけでお金を貸さない!
金銭トラブルで最も多い原因は、証拠が残らない「口約束」です。貸した側は「返すと言ったはず」と主張をするものの、相手が認めず、証拠がなく立証できないケースも多く見られます。
~トラブル予防のために必ず残すべきもの~
・金額
・返済期限
・支払い方法
・利息
・返済に関する双方の合意内容
必ず書面やメッセージで証拠を残しておくことが大切です。できれば、借用書を作成することが望ましいところです。
②返済条件は明確に取り決める!
お金を貸す理由、返済期日、返済方法(一括か分割か等)等、返済する際の条件を明確にしておくことが大切です。返済期日を決めないまま貸してしまうと「今は払えない」「落ち着いたら返す」と延々と返済を先延ばしにされてしまう可能性があります。
③相手の支払い能力を事前に確認!
返済の見込みがあるのかどうかを確認しておくことが大切です。
~確認しておくとよいポイント~
・現在の収入状況、安定した収入があるか
・借金の有無等
必要に応じて、保証人をつけてもうらうことができれば、回収の可能性も高くなります。
④返済が滞ったら早めに対応を!
返済期日を過ぎても支払いがない場合、放置をしてしまうと相手と連絡が取れなくなることがあります。まずは電話やメッセージで督促を行い、それでも応じない場合は、内容証明郵便による請求を検討するようにします。
⑤早めの相談が解決の鍵!
上記にも記載した通り、金銭トラブルは放置をすると解決が難しくなります。返済が滞り始めた段階、もしくは連絡が取れにくくなってきた段階で、早めに弁護士などに相談することをおすすめします。
当事務所長崎オフィスでは、借用書の作成、内容証明の作成、返済の督促や裁判等の対応を行っております。金銭トラブルでお困りの方は、まず当事務所長崎オフィスへご連絡下さい。
なお、長崎オフィスでは、金銭トラブルだけでなく離婚や刑事事件等の相談も受け付けており、経験豊富な弁護士がご相談者様に寄り添いご対応させていただきます。
初回相談は無料となっておりますので、お困りの場合は、まずは長崎オフィスまで電話いただければ幸いです。当事務所の弁護士が親身になってご対応させていただきます。

New Entry
Archive
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年1月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月