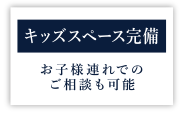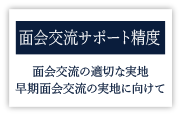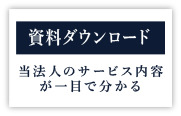- HOME
- 法律相談コラム
弁護士ブログ
2025/10/02
法人破産でやってはいけない6つの行為
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、多数の法人破産を取り扱ってまいりました。
企業経営が行き詰まったとき、「法人破産」は再出発のための重要な選択肢です。しかし、破産手続を誤ると、法的リスクや刑事責任に発展する可能性があります。
今回は、法人破産を取り扱ってきた弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスが、破産申立前に絶対に避けるべき6つの行為について解説いたします。
1.一部の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)
破産法では「債権者平等の原則」が定められており、特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済」として禁止されています。破産管財人により否認され、弁済が無効になる可能性が高く、悪質な場合は法的責任を問われることもあります。
事例紹介:偏った返済を回避し、円滑な破産申立に至った製造業のケース
精密部品の製造を行っていたA社は、主要取引先の突然の倒産により売掛金の回収が不能となり、資金繰りが急速に悪化しました。社長は長年付き合いのあった一部の取引先へ優先的に返済を試みましたが、当事務所が「すべての債権者を公平に扱う」という破産制度の基本を丁寧に説明。最終的には返済の優先を見送り、すべての債権者に対して中立な対応を取ることができました。こうした誠実な姿勢が評価され、破産管財人との連携も順調に進み、代表者個人も責任を問われることなく早期の生活再建に踏み出すことができました。
2.財産の隠匿・無償譲渡・安価での売却
破産前に会社の資産を意図的に減らす行為(財産隠し、無償譲渡、安売り処分など)は、債権者の利益を害する不正行為です。名義変更や親族・関係者への譲渡も偽装とみなされ、詐欺破産罪などの刑事責任に問われる可能性があります。
事例紹介:不適切な資産移転を防ぎ、トラブルの回避に成功した飲食業の事例
B社は複数の飲食店舗を展開していましたが、業績の悪化と過剰な借入により経営が行き詰まり、破産を検討する段階に入りました。破産直前、代表者は店舗内の厨房設備や什器を親族名義に移すことで資産の保全を図ろうとしていましたが、当事務所が介入し、こうした行為が破産法上の否認対象となる可能性や、最悪の場合は詐欺破産罪として刑事責任を問われかねないことを説明。リスクを正確に理解した代表者は、計画を中止し、すべての資産を適切に開示したうえで正式な破産手続へと移行。破産管財人との関係も良好に築かれ、従業員の雇用先紹介などの支援もスムーズに進行しました。トラブルを未然に防ぐことができた典型的な事例です。
3.破産予定を社外に漏らす
破産の検討段階で情報が社外に漏れると、資産の引き上げ、契約解除、社内混乱などのトラブルが発生しやすくなります。
破産手続の安定性を損なうため、情報管理には細心の注意が必要です。
4.返済の意思がない借入をする
返済の意思がないまま借入や取引を行うと、「計画倒産」とみなされ、破産申立が却下される可能性があります。
さらに、詐欺罪や詐欺破産罪として刑事責任を問われるリスクもあります。
5.資産を使い果たす
法人破産には申立費用や破産管財人報酬など、最低限の資金が必要です。
資産を使い果たしてしまうと申立すらできず、会社を放置するしかなくなるケースも。結果として、代表者個人や従業員・取引先に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
6.社長や役員名義への資産移転
会社資産を代表者や役員個人名義に移す行為は、実質的に財産隠しとみなされます。
破産管財人によって否認されるだけでなく、悪質と判断されれば刑事責任を問われることもあります。
法人破産は「誠実な経営判断」です。
借金問題や資金繰りの行き詰まりは、経営者にとって非常に苦しい状況です。
しかし、法人破産は責任逃れではなく、再出発のための正しい経営判断でもあります。
問題を先送りせず、法的に正しい手続きを踏むことで、代表者個人や従業員・取引先への影響を最小限に抑えることが可能ですので、まずは法律相談をされては如何でしょうか。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多くの企業様からご相談をいただき、丁寧に対応してまいりました。
初回相談は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」という方も、どうぞ安心してご連絡ください。
また、交通事故、相続・遺言、刑事事件、離婚・男女問題など、幅広い分野に対応しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィス
弁護士 寺町 直人
お客様の声
2025/09/19
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:良かった
弁護士に相談して:良かった
事務所の雰囲気:普通
今後何かあれば当事務所へ:相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス
お知らせ
2025/09/18
不倫・DV・モラハラで悩んだら弁護士に相談を
「配偶者の不倫が発覚した」
「暴力を受けているが、誰にも相談できない」
「モラハラに耐える日々に限界を感じている」
このようなお悩みを抱えて、離婚を真剣に考えている方は少なくありません。
そこで、不倫・DV・モラハラによる離婚についてご説明いたします。
1.配偶者の不貞行為で離婚・慰謝料を請求したい場合
不貞行為は、正当な離婚理由であり、慰謝料請求も可能です。
不倫で慰謝料を請求できる例として、以下のようなケースがあります。
・配偶者が不倫相手と肉体関係を持っていた
・LINEや写真など、証拠がある
・不倫によって婚姻関係が破綻した
・不倫相手が配偶者は既婚者であると知っていた
不倫の慰謝料は、一般的に50万~300万円程度が相場です。
別居・離婚の有無や不倫の期間などで金額が変動しますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
2.配偶者からの暴力に悩んでいる場合
DV(家庭内暴力)は、離婚原因として明確に認められています。
また、緊急避難・保護命令・慰謝料請求など、法的な対応が可能です。
DVに該当する行為は、以下のようなケースがあります。
・殴る・蹴るなどの身体的暴力
・無視や暴言などの精神的暴力
・外出や人間関係の制限
・生活費を渡さないなどの経済的支配
DVの場合、まずは身の安全を最優先にしてください。
弁護士にご相談いただければ、保護命令の申立てや、離婚調停の対応も可能です。
3.モラハラ(モラルハラスメント)による精神的苦痛が続く場合
モラハラは、言葉や態度による精神的虐待です。
近年、モラハラを理由とした離婚相談が増えています。
モラハラの具体例として、以下のようなケースがあります。
・「お前は無能だ」などの人格否定
・無視を続ける、話しかけても無反応
・友人・家族との連絡を制限
・一方的に責められ、謝罪を強要される
モラハラ離婚で重要なのは証拠の積み重ねです。
録音、メモ、メールの保存などを継続的に行うことが、法的な離婚・慰謝料請求の有力な証拠となります。
離婚は、人生を大きく左右する決断です。
不倫・DV・モラハラなど、つらい状況にいるなら、一人で抱え込まず、弁護士に相談することが第一歩です。
不倫、DV、モラハラは、我慢すべき問題ではありません。
法的に適切な対応を取ることで、自分と大切な家族を守ることができます。
人生を変える一歩を踏み出すために、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお気軽にご相談ください。
また、山本・坪井綜合法律事務所では、離婚相談だけでなく、不貞慰謝料請求、交通事故、刑事事件はもちろん、法人破産や個人破産、任意整理等の債務整理についてもご相談可能です。
どんなお悩みも、まずは山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご気軽にご相談ください。
お知らせ
2025/09/18
相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方へ
交通事故に遭った後、相手方の損害保険会社と交渉をする必要がありますが、思うように話が進まず悩んでいる方は少なくありません。
賠償額が低い、話がなかなか進まない、専門用語が難しく対応に不安を感じる……
【よくある相談としては】
①提示された賠償額が妥当か分からない
②治療費・休業損害などの証明書類をそろえるのが大変
③後遺障害等級の申請や認定に不安がある
④保険会社の専門的な言い回しが理解しにくい
⑤事故後の生活再建と並行して交渉を続けるのが精神的に負担
そんな時,弁護士に相談してみませんか?
【弁護士に相談するメリット】
①適正な賠償額の算定と交渉
②医療記録や事故証拠の収集支援
③相手方保険会社との交渉を代理して対応
④後遺障害等級認定の申請手続きサポート
⑤裁判手続きが必要になった場合の代理人としての活動
弁護士が代理人として交渉することで,相手方保険会社と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。
相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずにお困りの方は、一人で抱え込まずに早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債務整理,交通事故,離婚等,刑事事件,遺産整理など初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気初回相談を無料でお受けしておりますので,まずはお気軽にお電話ください。
お客様の声
2025/09/18
アンケート結果
ご相談目的:学校トラブル
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:事務所ホームページ
ご意見・ご感想:今回はお忙しい中お話をきいていただき、ありがとうございます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
長崎オフィス