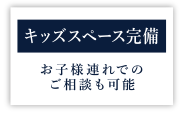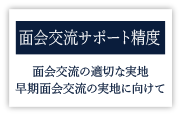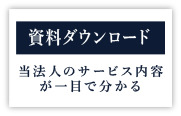- HOME
- 法律相談コラム
お知らせ
2022/04/01
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス新規事務スタッフ入所のお知らせ!!
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、本日新しく1名の事務局が入所しました。
長崎オフィスでは、弁護士坪井、ベテラン事務局の山下、そして新しく入所した佐々木の3名体制でご相談者様のお悩みに対応してまいります。
新規スタッフが入所したことで、長崎オフィスにおいて新たな風が吹き、事務所の雰囲気がより良いものになりました!!
まだまだ未熟な部分もありますが、少しでも早期に成長し、ご相談者様に寄り添えるよう指導してまいりますので、今後とも弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスをよろしくお願い致します!
一人で悩まずに新たな一歩をわたしたちと。
弁護士法人山本坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
お客様の声
2022/03/31
アンケート結果
ご相談目的:離婚問題
弁護士の説明:大変良かった
弁護士に相談して:大変良かった
事務所の雰囲気:大変良かった
今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい
事務所を選んだ理由:弁護士ドットコム
ご意見・ご感想:相談日程の調整の段階から、何とか合わせようとして下さっってる印象を受け、それだけでも心強かったです。困ったときはぜひ相談しようと思います。
弁護士ブログ
2022/03/29
相続の相談
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続問題の解決に力をいれております。
相続が絡むと、これまで仲の良かった親族も態度が一転して、険悪になることも少なくありません。
他人と争いになるのと、親族と争いになるのとでは、精神的負担は大きく異なります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の相続案件を取り扱ってきた弁護士の坪井が所属しており、相続問題について親身に相談対応させていただいております。
ご相談者様の精神的な負担が少しでも軽減させることができるように皆様のお力になれればと思っております。
相続の問題に悩んだらまずは当事務所の長崎オフィスにお気軽にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
弁護士ブログ
2022/03/28
離婚事件の取り組みについて パート4
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。
本日は,子の引渡しについてご説明します。
夫婦が別居する際,夫婦の一方が子を一緒に連れて行った場合に,他の一方が子の返還を求めることを子の引渡しといいます。
子の引渡し請求は,相手方が任意に応じてくれる場合には問題がないですが,相手方が子を一緒に連れて行っている以上,任意に応じてくれるということは基本的にはありません。そこで,その場合には,子の引渡しの実現方法として,調停または審判をしていくことになります。
子の引渡し請求が認められるためには,一般的には子の福祉の実現という観点から判断されることにはなりますが,その他にも父母の事情や監護補助者の有無等も考慮されるため,その判断はなかなか難しいだけでなく,早期に申立てをしないと子の引渡しが認められにくくなるということもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,土日祝日を問わず,子の引渡しに関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。
子の引渡しに関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
弁護士 坪井 智之
弁護士ブログ
2022/03/28
自己破産手続きにおける自由財産
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、自己破産手続を数多く取り扱っています。
自己破産というと、全ての財産を取られるというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、破産法は、その第1条で「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」とその目的について定めています。
つまり、多重債務等を抱え生活に困窮した債務者を救済し、経済的に立て直すことが自己破産の目的の一つとされているのです。
債務者は、当然ながら自己破産手続きが終わった後も生活していかなければいけません。
しかし、全ての財産を没収してしまうと生活もままならなくなってしまい、債務者の経済的更生という目的が達成できなくなってしまうため、自由財産が認められています。
破産法では、99万円以下の現金、法律上差押えが禁止された財産、破産手続き開始後に新たに取得した財産が自由財産として認められており、これらの財産は当然に自由財産として認められるという意味で、本来的自由財産と呼ばれています。
法律で定められている自由財産ですが、個々の破産者の状況によっては個別に判断し、裁判所が自由財産の範囲を拡張することができると規定していますので、自己破産を検討されている方は、自由財産の拡張など特別な手続きも必要となる場合もありますから、お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之