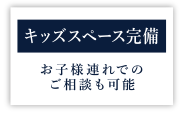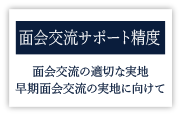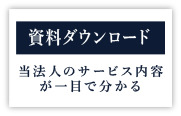- HOME
- 法律相談コラム
法律相談コラム
2022/02/16
少年事件に関するQ&A 1
Q子供が観護措置になったと聞きました。観護措置ってなんですか?
少年事件では、家庭裁判所が事件を受理した際、少年を少年鑑別所に収容することがあります。これを観護措置と言います。
少年鑑別所では、少年の処分を適切に決めるために、医学、心理学等の専門知識に基づいた検査などを行います。
少年が、少年鑑別所に収容される期間は、通常4週間です。
少年事件は、少年審判までの時間があまりなく、早期に弁護活動に着手しなければ充実した弁護活動ができません。お子様が逮捕された方は、早い時点で弁護士にご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、これまで多数の少年事件、刑事事件を解決してきた弁護士が在籍しておりますので、少年事件や刑事事件でお悩みの方はお気軽に長崎オフィスまでご連絡ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと
弁護士ブログ
2022/02/15
債務整理について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、債務整理案件を多数扱っています。
債務整理には自己破産、個人再生、任意整理の3つの種類がありますが、
今回は、自己破産をしても免除されないことになっている債務について、
ご説明したいと思います。
自己破産とは、裁判所に対して破産と免責許可の申立てを行い、最終的に免責許可を得ることで原則として金銭の支払義務が全額免除される手続きのことですが、すべての債務が免責されるわけではありません。
後述する債務が、法律で非免責債権として定められているものです。
・各種税金
・悪意の不法行為(詐欺や横領など)損害賠償
・故意や重大な過失で他人の生命や体を害した時の損害賠償
・養育費
・従業員への未払い給与
・故意に債権者名簿に記載しなかった債権
・罰金
これ以外に、生活保護の返還請求権も現在では非免責債権になっています。
また、故意ではなくても、交通事故の損害賠償金などは、事故に関する事情によって、非免責債権となるか、その支払いを免れることができるのかが変わってきます。
従って、裁判所がどのような判断をするかを予測して、サポートができる弁護士に相談することが大切と思われます。
借金問題でお悩みの方は、一人で悩まずに初回相談無料の当長崎オフィスにお気軽にご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
代表弁護士 坪井智之
法律相談コラム
2022/02/15
相続問題のQ&A 1
Q 夫が病気で亡くなりましたが、遺言書は残されていませんでした。家族は私と二人の子どもですが、相続手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
A 相続手続きでは、相続をする相続人と相続財産を確定することが必要です。
亡くなられた方(被相続人)が遺言書で相続人を指定していない場合は、原則、法定相続人が相続することとなります。
法定相続人とは、法律(民法)で定められた相続人のことで、配偶者や被相続人の子ども、父母、兄弟姉妹などが当たります。
法定相続人には、法律で相続順位が定められており、第一相続人は、配偶者とその子、第二相続人は、配偶者と父母、第三相続人は配偶者と兄弟姉妹となっており、配偶者は、常に法定相続人となります。
また、被相続人の子どもが先に亡くなられている場合などは、その子(孫)が子に代わって相続人となります。
ですから、あなたと二人のお子様は法定相続人に該当します。
注意しなければならないのは、生前に養子縁組をした養子や、認知した子ども等いる場合は、法定相続人に含まれるということです。
法定相続人を確定させるためには、亡くなられた人(被相続人)の生前から死亡に至るまでの戸籍を調べる必要があります。
相続財産については、亡くなられた方が所有していた現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、借金など、相続の対象になるすべての資産や権利、負債などをいいます。
また、賃貸人や賃借人など契約上の地位や損害賠償請求権などの権利、損害賠償義務などの義務、連帯保証人の責任なども相続の対象となります。
このような相続財産を確定する必要があります。
相続財産が確定すると、次に財産相続分となります。
相続分については、相続人双方の話し合いにより決定されますが、法定相続分が法律により定められており、相続の順位により異なっております。
| 相続順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 第一相続人 | 配偶者 | 2分の1 |
| 子 | 2分の1 | |
| 第二相続人 | 配偶者 | 3分の2 |
| 父母 | 3分の1 | |
| 第三相続人 | 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹 | 4分の1 |
なお、子、父母、兄弟姉妹が複数いるときは、その人数で等分されます。
ただし、被相続人と父母の一方を異にする兄弟姉妹の相続分は、他の兄弟姉妹の2分の1となります。
このように相続の手続きは、相続人や相続財産の調査にかなり手間を要しますし、相続人が多数おり、相続分の話し合いがまとまらなかったりすることが、多々あります。
そういった相続に関する手続きを、専門家の弁護士に相談し、依頼すれば、まとめて代行してくれますので、大変手間が省けます。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、相続に関するご相談を多数お受けし、解決に導いております。
まずは、当事務所長崎オフィスの弁護士にご連絡ください。
法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 9
Q 交際相手が、携帯電話の着信履歴やメールを見るなど、私の行動を監視し、気に入らないと家から出られなくします。どうすればよいですか?
恋人からの身体的・精神的・性的な暴力は、デートDVと呼ばれ、高校生や大学生等、若い男女の間でも頻繁に起こっています。特に行動監視等の「束縛」は若い人に多いと思われます。
DV防止法は、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力もDV防止法の対象となります。生活の本拠を共にすると認められるのかの判断は、同居期間の長短のみではなく、同居解消後に引き続き暴力を受けている方も保護の対象となります。
また、DV防止法以外にも加害態様によっては、刑法やストーカー規制法の対象となります。
このような交際相手からのDVでお悩みの方は、まずはお気軽に当長崎オフィスの弁護士までご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩を私たちと
法律相談コラム
2022/02/15
離婚に関する問題Q&A 8
Q 夫からの暴力を直ちに避けるためにはどうすればよいでしょうか。
夫から暴力を受けている場合には、身の安全を確保すべく、110番通報するのが先決です。しかし、様々な理由から警察には連絡しにくいという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、とにかく距離を置くことからはじめ、身の安全を確保すべきであるため、配偶者暴力相談支援センター等が運営している一時保護施設(シェルター)の利用も検討してください。
また、状況によっては、弁護士に相談し、弁護士が窓口となり、相手方と話を行い、保護命令の申し立てや調停の申し立てを行う等、弁護士を介在させることで相手方と距離を置くことができる場合もあります。
夫の暴力で悩んだらすぐに当長崎オフィスにお電話いただき、弁護士とご相談ください。
一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと