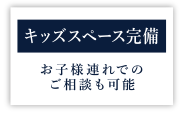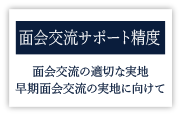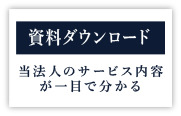- HOME
- 法律相談コラム
法律相談コラム
2024/04/02
民法の親子関係に関する法制度の改正について
民法の親子関係に関する法制度の改正について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、昨今頻繁に起こる法改正について、
弁護士間でしっかり情報を共有しております。
以下、改正された親子関係に関する法制度について説明します。
Q1 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止について
改正前の嫡出推定規定制度では、離婚等の日から300日以内に前夫以外の者との間の子を出産した女性が、その子が前夫の子と扱われることを避けるために出生届の提出をためらうという事態が生じており、それが無国籍者の生じる一因であったため、改正されることになりました。
従前の嫡出推定の規定は、婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとされていましたが、令和6年4月1日施行の法改正により、婚姻中に懐胎した子に加え、婚姻後200日以内に生まれた子も、夫の子と推定するとされ、離婚等の日から300日以内に生まれた子でも、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の推定するとされました。なお、母が再婚していない場合には、前夫の子と推定されることになります。
次に、女性の再婚禁止期間は、前夫の嫡出推定と再婚後の夫の嫡出推定との重複をにより父が定まらない事態を回避するための規定でしたが、上記の改正法の嫡出推定規定では、そのような事態が生じず、女性の再婚禁止期間を設ける必要がなくなったため、女性の再婚禁止期間について撤廃されることになりました。
女性の再婚禁止期間について法改正前は、女性は、離婚後100日間再婚することができないとされていましたが、令和6年4月1日の法改正により、撤廃されたため、離婚後すぐにでも再婚ができるようになりました。
Q2 嫡出否認制度について
嫡出否認の訴えとは、嫡出推定の規定により嫡出が推定される子について、父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えを提起しなければならないというものをいいます。
法改正前の民法では、夫のみに認められていた嫡出否認の訴えが、法改正により、子及び母にも認めることになりました。
改正前の民法では、生物学上の父子関係がない場合でも、子や母が自らの判断で否認することができず、母は、子が夫の子と扱われることを避けるために出生届を提出しないということがあり、このことが無国籍者の生じる一因であるとされているため、本法改正がなされました。
加えて、子の利益保護する観点からは、長期間にわたって子の身分関係が不安定になることは望ましくないといえるという観点から、嫡出否認の訴えのできる期間は1年とされていましたが、法改正に3年間に伸長されました。
法律上の父子関係の存否を左右する嫡出否認権の行使を是非ついて、嫡出否認権者において適切に判断するための機会を広く確保することも重要と考えられたため、法改正がなされました。
具体的には、否認権者は、夫に加え、子及び母、前夫(再婚後の夫の子と推定される子に関し)とされ、訴えの提起できる期間は、夫及び前夫は子の出生を知った時から、子及び母は子の出生の時から、それぞれ原則として3年間になりました。
なお。子は、一定の要件を充たす場合には、例外的に、21歳に達するまで、嫡出否認の訴えを提起できます。
Q3 認知無効の訴えの規律の見直しについて
法改正前は、訴えの提起できる者を、子その他の利害関係人と広く認められ、その期間制限もありませんでしたが、利害関係人が、父子関係の当当事者及びそれに準じる立場にある母が認知を認めている場合であっても、利害関係人がこれらの者の意思を無視して、無効の訴えを提起できる制度は相当でないと考えられ、訴えを提起できる者を子、認知をした父及び母に限定されました。
また、これまで期間制限がありませんでしたが、婚姻中の父母から生まれた子については、嫡出推定制度により父子関係を争うことが期間が厳格に制限されているにもかかわらず、婚姻していない父母から生まれた子については、認知の無効の訴えを提起できる期間に制限がないことは均衡を失するとの観点から、認知権者は、認知の時から7年間、母及び子は、認知を知った時から7年間に限定されることになりました。
Q4 上記Q1~3について、施行日前に生まれた子への法改正の適用について
改正法は、嫡出推定規定の見直しと女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出否認制度の見直し、認知の無効の訴えの規律の見直しに関する規定は、原則として令和6年4月1日以後に生まれた子に適用され令和6年4月1日より前に生まれた子には、改正前の規定が適用されます。
しかし、改正法の施行前から存在している無戸籍者の救済を図るため、令和6年4月1日より前に生まれた子についても、令和6年4月1日から1年間に限り、令和6年4月1日より前に生まれた子やその母が、嫡出否認の訴えを提起できることとされました。
法律相談コラム
2024/04/02
児童虐待防止のために民法が改正されました
児童虐待防止のために民法が改正されました。
これまで民法822条は、親権を行う者は、民法820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子の懲戒をすることができると規定されていましたが、法改正によりこの規定を廃止しました。
これまで懲戒権の規定は、児童虐待を正当化する口実に利用されることが多かったため、児童虐待を防止するべく、法改正がなされました。
そして、法改正により、子の監護及び教育における親権者の行為規範が明記され、民法821条は、子の人格の尊重、子の年齢及び発達の程度に配慮、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止の規定を明記しました。
なお、懲戒権が削除されることで正当なしつけができなくなるのかという疑問が生じますが、親権者は、民法820条が定めるこの利益のためにする監護及び教育として、子に対して社会的に許容される正当なしつけをできると考えられています。
法律相談コラム
2022/10/20
過払い金請求について
「昔、ちょっと借りてただけなんだけどね」
「こんなに戻ってくるなんて思ってもみなかったよ」
CMなどでよく耳にするのではないでしょうか
過払い金請求とはなにかご存じですか?
貸金業者は、お金を貸しその分の利息を得ることによって利益を得ています。
金利が高ければ高いほど貸している側は多くの利益を得られることになります。
しかし借りる側は金利が高ければ高いほど、返済の負担が多く負担になってしまいます。
歯止めをかけるために、利息制限法によって利息の上限利率が決まっています。
元本10万円未満の場合、上限利率20%
元本10万~100万円未満、上限利率18%
元本100万円以上、上限利率15%
今は上限の利率が決まっていますが、2010年に出資法が改正されるまでは29.2%(グレーゾーン金利)なら利息制限法を超える金利で貸し付けることが可能であり、条件があるものの利息制限法を超える金利での支払いも有効なものとされていました。
高利を取る消費者金融が多く、歯止めをかけたのが2006年の最高裁判決、
払い過ぎた利息は元本に充当され、それでもなお残るものは過払い金として借主が取り戻せる可能性がある。これが過払い金請求にあたります。
過払い金が発生するのは、2010年6月17日以前の取引であり改正前民法が適用されるため、消滅時効の期間は10年であり
過払い金請求する権利は、最後に返済や借り入れをした日から10年であり、時効にかかって消滅します。
2020年4月1日に、消滅時効に関する民法が改正され2020年4月1日以降に生じた過払い金の場合、消滅時効は
① 最後に返済や借り入れをした日から10年
② 過払い金を請求できると知った日から5年
どちらか早い方で成立します。
自己判断はせず早めにご相談されることをおすすめいたします。
どんなお悩みでも山本・坪井綜合法律事務所はご相談を受けております。
お気軽にお問い合わせください。初回相談料でご相談をお受けします。
一人で悩まずに新たな第一歩をわたしたちと一緒に
山本・坪井綜合法律事務所があなたのお悩みに寄り添います。
弁護士法人 山本・坪井綜合法律事務所
法律相談コラム
2022/10/03
自己破産について
債務整理には、自己破産・任意整理・個人再生がありますが、今回は自己破産についてご説明します。
自己破産とは、借金を返せなくなったときに、一定の財産を債権者たちに平等に分配する一方で、「免責」を受けることで、借金を全額免除してもらう手続きのことをいいます。
自己破産にはメリットもあればデメリットもあります。
<メリット>
・多重債務問題が全面的に解決する。
・破産をしても、一定の財産は手元に残すことができる。現金では99万まで手元に残すことができ、日常生活に必要な財産等も残すことができる。
<デメリット>
・破産したら、ブラックリストにのり、借金やクレジットカードでのショッピングができなくなる。
・一度破産をすると、7年間は自己破産ができなくなる。
自己破産にはメリットやデメリットがありますので
多重債務でお悩みの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談をすることで、その方にあった債務整理の方法をご提案することができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、初回相談を無料で承っております。
事前御予約制となっておりますので、ご相談ご希望の場合は、まずはお気軽にお電話くださいませ。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス
法律相談コラム
2022/04/11
刑事事件の身元引受人について
Q 会社の同僚が刑事事件を起こして、警察で取り調べを受けているようです。身元引受人になってもらいたいと連絡がありましたが、身元引受人とはどういったものですか?
A
1 刑事事件の身元引受人とは
刑事事件における身元引受人とは、「一度警察に捕まった被疑者が、間違った行動をとらないよう監督する人」のことを言います。
ここで言う「間違った行動」の例として挙げられるのが、逃亡や証拠隠滅、警察署への不出頭、さらなる犯罪行為、被害者へのお礼参り、自殺等があげられますが、被疑者や被告人がこのようなことをしないように監督する人が、身元引受人です。
2 刑事事件の身元引受人が必要となる場合
(1)取調べを受けたが逮捕されなかった場合
警察署で取調べを受けた後、警察が逮捕するまでの必要はないと判断した場合、身元引受人が必要となります。警察から身元引受人に連絡があり、警察署に本人を迎えに行くこととなります。
微罪処分や任意捜査(在宅捜査)の場合が該当します。
(2)逮捕された後、警察の判断で釈放される場合
警察に逮捕されたけど、検察に送致されず釈放される場合に、身元引受人に警察から連絡があり、警察署まで迎えに行きます。
痴漢や交通事故、交通違反で現行犯逮捕された場合が多いです。
(3)逮捕されたが、検察官が勾留請求しなかった場合
警察が逮捕し、すぐに釈放しない場合は、48時間以内に身柄を検察官に送致する手続きとなります。送致を受けた検察官は、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断した場合は、さらなる身柄の拘束をする勾留の請求をしません。勾留の請求をしなかった場合は、逮捕された被疑者は釈放となりますので、検察官の判断で、身元引受人に連絡され、迎えに行くこととなる場合があります。
(4)裁判官が勾留請求を却下した場合
検察官の勾留請求に基づき、裁判官が勾留の必要性を判断し、必要ないと判断したならば、勾留却下となり、釈放となります。裁判官が勾留の必要性について判断するにあたって、身元引受人についても考慮されます。
(5)保釈請求をする場合
刑事事件で起訴されたならば、事案により保釈を請求することができます。保釈を請求するにあたり、身柄引受人を立てることで、保釈が認められる可能性が高くなります。
(6)執行猶予を求める場合
刑事事件で起訴され裁判になった場合、勾留中の被告人について執行猶予を求める際、身元引受人に情状証人として裁判所に出頭してもらい、今後の被告人を監護する意思があることや、その具体的な監護方法について話してもらい、執行猶予を求めていきます。
(7) 刑務所から仮釈放(仮出所)する場合
実刑の判決を受け、刑務所に服役した場合、刑期の終わりが近づくと、本人の反省や更生意欲の度合いにより、仮釈放が認められることがあります。仮釈放されるかの判断に、身元引受人がいるかどうかが重要な判断要素となります。
3 身元引受人になる条件
刑事事件の身元引受人になる条件については、法律で定められているわけではありませんが、誰でもよいわけではありません。実務上は、本人を監督するにふさわしい人が身元引受人になります。
身柄引受人として、ふさわしいと判断される可能性の高い順にお話していきます。
(1)同居の配偶者などの家族・親族
同居の家族・親族は、最もよくある身元保証人となります。配偶者がいれば配偶者、配偶者がいない場合は両親や兄弟、子どもなど同居の家族が最も理想的です。
同居していることで、日常的に本人とコミュニケーションをとる機会があり、本人を間近で監督することが可能であることから、本人の行動に目が行き届き、監督もしやすく、監督者としてふさわしいものと判断されます。
(2) 同居していない家族・親族
同居の家族がいない場合や刑事事件になっていることを同居の家族に知られたくない場合に、実家の両親や近くに住んでいる兄弟姉妹が身元引受人となる場合もあります。
同居していないことから、監督の実効性の点で劣るところがありますが、家族であることから問題ないものと思われます。
(3)職場の上司
一人暮らしや実家が遠方の場合、身寄りがない場合などの時は、職場の上司に身柄引受人になってもらう場合があります。
職場の上司は、日常的に本人とコミュニケーションをとっており、職場の上下関係からも生活指導を受けることができることから、身柄引受人として問題ないものと思われます。
しかし、職場の上司などに身元引受人を依頼すると、職場に刑事事件を犯したことが知れてしまい、職場で何らかのペナルティを受ける可能性がありますので、注意が必要です。
(4) 彼女
家族や職場の上司にも、刑事事件となっていることを知られたくない場合は、彼女に身柄引受人をお願いすることがあります。
彼女と言っても、様々な関係があり、婚約している彼女や同棲している彼女であれば問題ないものと思われます。
(5)友人、知人
他に適切な身元引受人がいない場合は、友人や知人に身元引受人になってもらうことがあります。しかし、友人、知人と言っても、日ごろから本人と連絡を取り合っていることが前提となり、単なる知り合いや何年も連絡を取っていない友人、知人は身柄引受人として認められるのは難しいものと思われます。
4 身元引受人の役割
刑事事件における身元引受人の役割は、前にも述べた通り、間違った行動をしないように監督することです。
(1)逃走や証拠隠滅をさせない
身元引受人の主な役割として、被疑者本人に逃走や証拠隠滅をさせないことです。
被疑者を一人で帰宅させると、どこか遠くへ逃走したり、事件に関する証拠物を処分したり、隠ぺいしたりする可能性があります。
そのため、捜査機関は、被疑者の家族やよく知る人物などに身元引受人となってもらい、逃走や証拠隠滅しないように監視してもらいます。
(2)取調べや裁判に出頭・出廷するように促す
警察や検察から取調べなどの呼び出しがあった場合は、応じるように促すのが、身元引受人の役割の一つです。
また、起訴された場合は、公判となり、被告人本人が裁判所に出廷しなくてはなりませんので、身元引受人は、裁判所への出廷を促さなくてはなりません。
(3)社会への更生をさせる
身元引受人は、犯罪を犯した被疑者を更生させる役割も担っています。
特に、窃盗事件や薬物事件などは、再犯性が高いので、病院や更生施設等に付き添うなど、再犯しないように注意するとともに社会への更生の役割も求められます。
5 身元引受人のデメリット
刑事事件の身柄引受人になった場合、法的にデメリットはありません。たとえ、本人が逃走したり、証拠をいん滅したとしても、身元引受人がそれに積極的に協力していない限り、法的に処罰されることはありません。
しかし、保釈中、被告人の保釈金を身元引受人が立て替えていた場合に、もし本人が逃走や証拠隠滅をすると、保釈が取り消され、立て替えていた保釈金は没収されます。
6 身柄引受人を降りることの可能性
身柄引受人自体は、法的な制度ではないので、いつでも辞めることができます。
ただし、一度その人の身元引受人を辞めた場合、次にその人の身元引受人になろうとしても認められない可能性があります。
その人が別の身元引受人を立てることが出来なければ、身柄を長く拘束されたり、保釈されなかったりして、不利益な結果となる可能性があります。
7 弁護士の身柄引受人
弁護士であっても、身柄引受人になることは可能です。
弁護士が本人の自首に同行して警察署に行った時、身柄引受人になる場合や、警察からの任意出頭の要請があった時、その前日までに弁護士が警察の担当者に対し、弁護士の身柄請書を送っておく場合等です。
なお、本人が逮捕された時は、弁護士は身元引受人にはなれません。
以上のとおり、身元引受人になることに対して、それほど心配する必要はありません。
いつ自分が犯罪者扱いをされたり、犯罪に巻き込まれるか分かりません。
そんな時、頼りになるのが、弁護士です。
当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスには、刑事事件に強い、経験豊富な弁護士が在籍しております。
また当事務所は、刑事事件の専門的な事務所であり、素早い立ち上がりで対応してまいります。
刑事事件を起こしたり、巻き込まれた方は、まず当事務所にご連絡ください。