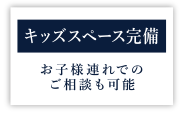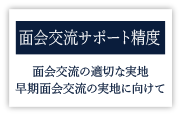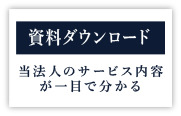離婚問題
離婚に関する問題
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの離婚のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの離婚のご相談に対する想いや取り組み等について記載しておりますので、是非最後までご覧ください。
当事務所長崎オフィスの離婚相談に関心をいただけた場合には、是非離婚専門サイトまでご覧ください。
あなたは離婚するか否か、離婚するためにはどうしたらよいか等でお悩みではありませんか?
離婚するか悩んだ時、あなたは誰に相談しますか?周囲に相談できる方はいますか?
離婚に関する家庭内の紛争に関して、なかなか友人や親族に相談できないという方も多いのではないでしょうか。
誰も知らない利害関係のない、そして守秘義務がある弁護士に相談されるのが一番良い相談相手です。だれにも相談できないことだからこそ、弁護士に相談して、離婚に関する法的問題だけでなく、離婚後の生活についてや離婚することのリスクなどについても、弁護士であれば的確にアドバイスを行うことができます。
離婚するか否か等離婚に関してお悩みの方、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスまでご連絡ください。
詳細については、下記離婚専門サイトをご覧ください。
長崎オフィスに所属している弁護士は、離婚事件や離婚に関する養育費請求、婚姻費用分担請求、子の引き渡し請求、監護者指定の請求、離婚に関する慰謝料請求等の解決実績が多数であり、特に、子供の親権の問題や面会交流に関する問題に力を入れております。離婚をしたいなと考えた場合、いろいろと動く前に、まずは弁護士へご相談下さい。離婚するか迷っている状態で弁護士へご相談することもお勧めします。どのように手続きを進めるのがよいのか、離婚に際して、どのような点が問題となるのかを早い段階でしっかりと検討しておくことが離婚を少しでもより良い形で行うためには重要です。
離婚に関して悩みが生じたらまずは弁護士に相談しましょう。相談する時期が早いということはありません。早期に弁護士に相談することがより良い解決につながります。
離婚には、各種手続きがあります。協議離婚、調停離婚、審判離婚,裁判離婚等の手続きがあり、どの手続きを行うのが最適であるか、ご相談者様の状況に応じた適切なアドバイスを弁護士が行います。離婚に関して、どのような手続きを取るかによって大きく結論が異なる場合もあるため、離婚に関する手続きは慎重に判断する必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚や離婚に関する問題でお悩みの方に寄り添い、離婚問題に関するストレスから少しでも解消できるようにしたいと思っております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚や離婚に関する相談は初回相談料無料でお受けしており、初回の無料相談だけでも全く問題なくお受けしておりますので、相談料などのご心配もございません。
他の事務所で相談されている方や他の事務所にご依頼されている方のセカンドオピニオンとして無料相談をしていただいても構いません。お気軽に当事務所長崎オフィスへお問合せください。
離婚について一人で悩まずに弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスと一緒に新たな第一歩を!!
離婚について考えたらまずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへご連絡ください。
子どもに関する問題
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、離婚の問題に力をいれておりますが、特に、子どもに関する問題について力を注いでおります。
中でも、親権問題や面会交流に関する問題、子の引き渡し請求問題、監護者指定問題、親権者変更問題等の子どもに関する問題に関心を持ち、解決に尽力を注いでおります。子どもに関する問題については、離婚に関する法的問題は当然ながら、それに加えて、個別具体的な子どもの福祉についても考える必要があり、単純に法律問題だけ計り知れない、慎重な配慮が必要になってきます。
子どもの立場を尊重しつつ、何が子どもにとって一番幸せであるかを常に考えることに重点を置き,双方当事者の法的な主張をまとめていく必要があります。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、弁護士坪井を中心にカウンセリングに関する知識、資格を学び、事務所全体でそのノウハウを共有することで子どもに関する問題について,さらに一歩深く考えるよう意識的な取り組みを行っております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、福岡オフィス、香川オフィスとの連携も図り、相手方が遠方の場合に,他のオフィスの弁護士が対応することで出張費用などの軽減を図ることもでき、また、手続きも円滑に行うことができます。他の支店があるからこそできる取り組みであり、実家に帰っていて,四国や福岡に住んでいる相手方に対して、離婚調停などを実施したいと考えている場合には、是非、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにご連絡ください。
当事務所長崎オフィスの理念に共感して頂けた方は、是非、当事務所長崎オフィスまでご連絡ください。離婚に関する問題、特に子どもに関する問題についてお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスにお気軽にご連絡ください。
離婚問題と一言でいっても、離婚に関する問題は多岐にわたります。親権、面会交流、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割、子の引き渡し、監護者指定,親権者変更等の様々な争点がありますが、主に、子どもに関する問題とお金に関する問題に分けることができます。
以下、各用語や問題点について簡潔にご説明いたします。
親権
親権とは、親が未成年者の子どもを一人前の健全な社会人に育成し、それまでの間、子どもの財産管理や法定代理をする職務上の役目のことを言います。夫婦が離婚する場合には、必ず親権を片方の親に定める必要があり、日本において、現在では,共同親権は制度上認められていません。(なお,現在,国会では共同親権についての立法について協議しており、今後共同親権等の制度変更の可能性はあり得ます)親権者でないからといって、決して親でなくなるわけではありませんが、親権者でないことで子どもに関する決定権を失うことになるため、様々な制限が事実上課されることがあり(例えば、子どもと会える頻度など)、親権者をどちらにするかは非常に重要な問題となっております。
夫婦間において、親権に争いが生じた場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、家庭裁判所の調査官の調査を経て、家庭裁判所の調査官の調査報告書を参考に、どちらを親権者と指定することが相当であるかを判断していくことになります。
家庭裁判所に申立てを行い、調査官の調査を実施していく中でも、様々な難解な法律用語や手続きの進行があります。下記で親権者を判断される要素についてご説明しますが、その判断を実質的に実施するのは家庭裁判所の調査官であり、家庭裁判所の調査官が出す調査報告書は、最終的に裁判官が判断するに際して非常に重要になってきます。
その家庭裁判所調査官とのやりとりなどでご不安を抱えている方は多数いると思います。家庭裁判所の調査官とどのような話をしたらよいか、調査官から聞かれている言葉の意味がわからないなど、様々な法律要素があるため,当事者だけでは不安に感じることが多いでしょう。
是非、一度弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士にご相談いただき、その不安を解消しつつ、調停手続きを進めていくことをお勧めいたします。
そして、親権を判断するに際しては、様々な要因が考慮されますが、重要なポイントとしては、①別居前の監護状況 ②現在の監護状況 ③今後の監護方針 ④子どもの意思があります。
①別居前の監護状況について
別居以前、夫婦のどちらがどのように監護していたのか、これまでの監護実績が考慮されたうえで,親権者が判断されます。
親権者を判断する際、母親が有利であるという点をよく耳にすると思いますが、このような点が考慮されております。すなわち、女性が専業主婦であったり、仕事を抑え子どもの養育監護に力をいれていたりするケースが多いため、従前の監護状況を踏まえると母親が親権者と指定されやすくなります。
しかし、昨今、父親の育児休暇取得の推進や女性の社会進出等の観点から今後は、従前の主たる監護者についても父親が主たる監護者であると判断されるようになる可能性があると考えられます。
そのため、両親どちらであったとしても子の出生後,子供とのかかわりをしっかりもち,養育監護していくことが親権者を定めるに際しては重要になってきます。
②現在の監護状況
離婚の話し合いをする際、一般的には夫婦は別居することが多く、その場合、片方の親と子どもは一緒に生活をすることになります。家庭裁判所の調停の手続きは相当期間時間を要しますが、その手続き中にも実際に子どもと生活している方の親は,これまでから変化した生活が子どもとの生活によって安定してきます。その安定した生活状況、すなわち現在の監護状況について問題がないかも親権者を指定する際には考慮されることになります。
このように現在の監護状況が考慮される関係で子供の連れ去りが実施されるケースが多くなっております。しかし,子供を連れ去ったと判断された場合には、親権者と適切性を欠くと判断される可能性があるため,連れ去りと判断されないようにしっかりと手続きの手順を踏むなど実施していく必要があります。違法な連れ去りは最終的に不利益に働く可能性があり,子供の福祉の観点から相当ではないため、絶対にやめましょう!!
③今後の監護方針
夫婦が離婚するとこれまでの生活とは大きく生活態様が変化することがあります。例えば、家の転居や学校の転校、養育監護する親の経済状況等です。
離婚後は親権者が中心となって子どもの養育監護を行っていく以上、実際に子どもを育てて行く環境が整っているのか、継続して育てていくことが可能であるのかを判断していく必要があります。そのため、今後の子どもの養育監護をどのように行っていこうと考えているのか、養育監護の協力者(養育監護者の父母による監護の協力の有無等)の有無等を踏まえ、監護者を指定することになります。
将来にわたる子供監護について子の意思を尊重しつつ、どのようにしていくべきか当事者はしっかりと考え、それを表現していく必要があります。
④子どもの意思
子どもの意思のみで親権者が指定されるものではありませんが、子どもの気持ちも親権者を指定するに際して重要な要素となります。ただし、一般的に子どもの意思は、15歳前後を基準に考慮されています。
理由としては15歳前後で子どもは自分の将来について、自己で判断することができるだけの意思決定能力が養われてくるためです。
以上のように、夫婦間において、親権者をいずれにするべきか争いが生じた場合には、上記①~④等の事情を総合考慮した上で夫婦のどちらを親権者と定めるべきか判断されることになります。
子どもの親権はいずれの当事者に指定するか非常に重要な問題です。どちらの親が親権者になる場合でも両親が子どもとの関わり方などをしっかりと考え、子どもの親権をどちらにするべきか、子どもにとって何が一番の幸せかを十分に考えいくことが非常に重要です。
面会交流
面会交流とは、子どもを養育監護していない親が子どもと会ったり、交流したりすることをいいます。 本来、離婚の成否にかかわらず、子どもにとって親であることは変わらない以上、子どもと十分に会う権利があることはいうまでもありません。 しかし、離婚や別居している夫婦の場合、子どもは両親の夫婦間のトラブルに挟まれ、心理的な負担は非常に大きなものであり、非監護者と会いたいという気持ちを持っていても、それをうまく表現できない場合もあります。 面会交流においては、子どもは一緒に生活していない親と会ったり、電話で話したりすることで、子ども自身の成長が期待できる反面、子どもが一緒に住んでいる親の顔色を伺うなどの精神的な負担がかかることがあります。 そこで、面会交流について、どの程度、どのように子どもと関わっていくことが子どもにとって良いのか、両親がしっかりと話し合い、決めていき、子どもにとってストレスのない面会交流を行うことで、子どもが精神的に安定し、成長できるようにする必要があります。 面会交流の内容について、場合によっては細かく定める必要があります。例えば,毎週何曜日の何時から何時まで等。しかし、家庭裁判所の調停の手続きによっては、ざっくりとした内容しか定めない場合があるため、適切な面会交流が定められているとは言えないケースが散見されます。 そこで、調停手続きに弁護士が介在することで、子どもの面会交流をどのような内容にすべきかしっかりと意見を述べ、適切な面会交流を求めていくことで、子どもの権利を守ることができます。 面会交流の取り決めは、必ず書面に残し、できるならば公正証書や調停調書として記録に残すべきです。後々に、あれは言ったはず、これ言っていない、これは違うとかの食い違いが出てきても公正証書があればそれを未然に防ぐことができるからです。口約束ではなく、必ず書面に残すことをしましょう。 面会交流の取り決めといっても、多種多様です。通常であれば、月1回程度の面会交流を認めるという記載程度に留めることが多いですが、具体的に第2土曜日の午前9時から午後12時までと言ったように、具体的に定める場合や、学校行事に参加を認めるというような内容などの具体的な条項を追加して定めることも多々あるため、どのような条項をいれるのがよく、入れることができるのかについて弁護士にしっかりと事前に相談しておく必要があります。
具体的には、以下の①から③等を少なくとも定めます。
①面会交流の内容
日帰りの場合や、宿泊を伴う面会交流などが考えられます。手紙や電話、SNSのやりとりを認めるかなども決めておきましょう。
②面会交流の頻度
週又は月に何回面会交流を実施し、1回につき何時間程度の面会交流を実施するか、宿泊を伴う場合には何泊するかなども必ず決めておきましょう。夏休みなどお子さまが長期の休みがあるときには、一定期間の宿泊を伴う面会交流を実施することも考えられます。
③その他
待ち合わせの場所や、電話やテレビ電話の利用の可否、学校行事の参加の可否、プレゼントに関する取り決め、事情が変わった場合の連絡先などを取り決めておくことが考えられます。
【注意】相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、面会交流をすることが、子どもの最善の利益に反する場合には、面会交流を行う必要はありません。あくまでもお子さんの健やかな発達のためであり、危害がある恐れがある場合は、面会交流中止または条項をより慎重に定める必要があります。
面会交流は長い間にわたって行われるもので、時間の経過とともにお子さんは成長し、養育環境も変化します。取り決めを守って安定した交流を行うことに加え、状況に応じて話し合い、協力し合いながら、子どもにとって最もよい面会交流をおこなっていくことが大切です。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、子が親と充実して会うことができる環境づくりのサポートを行います。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦及び未成熟の子を含む婚姻共同生活を営むために必要な一切の生活費のことをいいます。具体的には、衣食住に関する費用、交際費、教養娯楽費、老後の準備費、子の養育費が含まれると一般的に考えられています。
これは夫婦が別居した際、一方当事者が他方当事者の生活を維持すべく、支払う費用です。
実務上では、婚姻費用は、請求した時点で支払い義務が生じるため、別居後すぐに請求することが重要となってきます。
他方で、有責配偶者からの婚姻費用分担請求等については、婚姻費用の支払いを拒絶できることもあります。なお,子供がいる場合,婚姻費用分担請求の中には養育費相当が含まれており,仮に有責配偶者からの婚姻費用分担請求であったとしても養育費相当分までは拒絶することは法律上できません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、婚姻費用の調停のご依頼を受けることが多く、婚姻費用について適正金額がいくらなのか算定し、適正金額を要求していきます。
また,過剰な婚姻費用を請求された場合等,適正な婚姻費用になるよう調停手続きなどにおいて当事者の主張を代理人が代弁いたします。
養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを言い、離婚後非親権者から親権者に対して支払われる費用のことをいいます。
養育費の額について問題になるケースが多いですが、実務上は裁判所が発行している養育費算定表をベースとして定められることが多いため、養育費の額について知りたい方はまずは裁判所のホームページをご参照いただき養育費の算定額をご確認ください。
お子さんのために養育費(①金額 ②支払期間 ③支払時期)についても定める場合、以下の点を調停調書や公正証書等に残すことが必要です。
①金額
原則として話し合いで決めることになります。裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にしましょう。
②支払期間
支払の始期と終期を決めておきましょう。終期については、大学等への進学の可能性も踏まえ、その子が経済的に自立することが見込まれる時期を考え、お子様の成長のために十分な期間を設けておくようにしましょう。終期を定める場合には必ず、「〇年〇月〇日まで」とか「22歳に達した後の3月まで」などと、具体的に定めましょう。
③支払時期
支払う時期を必ず決めましょう。毎月一定の金額を支払う例が多いようですが、経済状況等によりある程度の期間の分を一括して支払うことも可能です。
④その他
毎月の定額の養育費とは別に、入学金や大学等の授業料、特別な出費が生じた場合に、どのように父母が負担するのかも必ず決めましょう。お子さんが健やかに成長するためには、いろいろとお金が必要になるものです。
個別具体的な事情の下での養育費の額等定め方については、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士までお問い合わせください。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活の間に夫婦が協力して蓄積した財産を、公平な観点から分けることをいいます。
財産分与は原則として2分の1の割合で分与されますが、どこまで財産分与の対象財産に含まれるのか、具体的にどのような分配をするのか、住宅ローンがある場合の対応はどうすればよいのかなど財産分与は多岐にわたる争いになる可能性があります。
また、一方当事者が財産を有していることは明らかであるが、どこにあるかわからないようなケースでは、どこにあるか探す必要があり、そのためにどのような手続きをすべきかなども弁護士からアドバイスいたします。
財産分与についてどのように進めてよいかお悩みの方は、当事務所長崎オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
慰謝料
慰謝料とは,離婚する際、一方当時者に不貞や暴力などの有責性がある場合に請求することができる精神的苦痛を慰謝するための損害賠償金です。
暴力、精神的なDVや不貞等慰謝料の請求の原因となりうるものがあります。
慰謝料請求は様々な要素が考慮されて判断されるため、離婚の際、慰謝料請求をしたいと考えている方、また慰謝料請求をされて納得のいかない方は当事務所長崎オフィスまでご連絡ください。
子の引き渡し及び監護者指定
一方当事者が別居する際、他方当事者の同意なく、子どもを連れて別居したような場合や別居中一方当事者が子どもを養育していたが、急に他方当事者が現れ子どもを連れ去ったような場合、子の引き渡し請求や監護者指定請求を行うことになります。
離婚するまでの間は、本来共同親権者であるためいずれも養育監護する権利はありますが、子どもの福祉を考慮しつつ、別居した際にはどちらかが養育監護を行う必要があります。
そこで上記のような場合には、早急に子の引き渡し請求や監護者指定の調停又は審判の申し立てを行い、争っていかなければなりません。
子どもの監護権,子の引き渡しについてお悩みの方は,まずは当事務所長崎オフィスにご連絡ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、子の引き渡し請求や監護者指定請求の申し立てを排斥したい方のご相談もお受けしておりますので、子の監護問題でお悩みの方は当事務所長崎オフィスまでお電話ください。
よくある質問について
養育費や面会交流の取り決めをしなければ離婚することはできませんか?
養育費や面会交流の取り決めをしなくても離婚することはできます。しかし、民法には、離婚の際に両親が協議で定めるべき事項として養育費の分担や面会交流が定められています。また取り決める際に、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと定められています。
離婚という結論を出すまでには、様々ないきさつや事情があり、親にとっても、それを乗り越えて新しい生活を築いていくことは大変なことですが、それは子どもにとっても同じことであり、子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長することができるためにも,養育費や面会交流の取り決めは必須です。また離婚した後でも取り決めをすることはできます。
なお,現在の法律では,共同親権は認められていないため,離婚する際には必ず両親のいずれかを親権者と定めなければ離婚することができません。
養育費の取り決めはどのように進めたらよいですか?
養育費の金額等について,まずは当事者間で話し合いましょう。養育費の金額、支払期間(例 〇年〇月~〇年〇月まで)、支払時期(例 毎月〇日)、振込先などを具体的に決めておきましょう。養育費の金額が適正か否か,養育費以外に学費などの取り決めをしたい方など,一言に養育費と言っても様々な問題を含んでいるため,養育費を定める場合には一度弁護士にご相談することをおすすめします。
そして,養育費の取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、必ず書面を残しておきましょう。養育費の取り決めを一定の条件を満たす公正証書(執行証書)によってした場合には、実際に養育費の未払いが生じた場合に執行の手続きを利用することもできます。
公正証書は公証役場で作成することができます。公正証書についてはお近くの公証役場か当事務所長崎オフィスにお問合せください。
離婚に相手が話に応じてくれません。または話し合いをしていますが、まとまりません。どうしたらよいでしょうか。
家庭裁判所の調停手続を利用することができます。家事調停手続は、夫婦、親子などの間のもめ事について、裁判官と民間から選ばれた調停委員が間に入り、非公開の場で、話し合いによって妥当な解決を目指します。
調停手続きは,一方当事者が欠席した場合については,進行することができず,離婚は成立しません。しかし,離婚に関して,法律は調停前置主義をとっており,必ず調停を先行させなければなりません。調停を実施しなければ,離婚裁判へ移行することができないため,調停手続きを行う必要があります。
話し合いによって離婚が成立しない場合には,調停手続き,そして,離婚裁判へと移行することになりため,早めに長崎オフィスの弁護士にご相談ください。
家事調停の申し立てをする費用と期間はどのくらいかかりますか。
養育費についての家事調停を申し立てるに当たっては、子ども一人につき1,200円(収入印紙で収納する必要があります。)必要となります。養育費に関する家事調停手続については平均的な審理期間は、約6か月程度と言われています。
離婚前の別居中でも生活費の請求はできますか?
はい、できます。離婚前でも、別居して子どもを育てている場合には、子どもを育てている方の親は、他方の親に「婚姻費用の分担請求」により、育てるのに必要な費用の支払いを求めることが出来ます。
婚姻費用の請求は,当事者の話し合いによって決めることもできますが,話し合いができない場合には調停手続きを実施することになります。そのため,家庭裁判所に婚姻費用分担請求の申立を行う必要があります。婚姻費用については,通常申立を実施した月より請求が認められるため,迅速な申立てを行う必要があります。
また,婚姻費用に関しては,婚姻費用算定表がありますので,そちらを参照していただくことで婚姻費用分担請求で認められるであろう概ねの金額を算出することができます。
婚姻費用分担請求をしようと思われたらまずは当事務所長崎オフィスの弁護士にご相談ください。